最近、物価がじわじわ上がっているのを感じませんか?昔は100円で買えた缶コーヒーも、今では130〜140円。100円で買えるものは減ってきています。
こうしたお金の価値が下がるインフレや円安に備える方法のひとつが金を持つことです。ただ、いきなり金貨やインゴットを買うのはハードルが高いですよね。
そこで注目されているのが純金積立。少額から始められ、自動でコツコツと続けられる仕組みで、初心者でも“ほったらかし”で資産を守れるのが魅力です。
 こうじ
こうじこの記事では「純金積立とは何か?」という基本から、メリット・デメリット、さらに楽天・SBIなど主要サービスの比較までをわかりやすく解説します。
インフレから家族のお金を守りましょう!
金を保有することの意味:インフレから資産を守る
金を保有することは結果として資産をインフレから守りますが、以下の3つの理由があります。
- 通貨は価値が下がるという宿命
- 金の持つ「価値保存」という性質
- 金は圧倒的に安定した物質



誰にでもわかるように解説します!
通貨はインフレで価値が下がる宿命:貯金だけでは目減りしてしまう
円やドルといった国が認めた通貨は、長い目で見ると価値が必ず下がってしまう特徴があります。なぜなら、国や中央銀行は必要に応じて新しく通貨を発行できてしまうからです。
最初の例では、自動販売機で缶コーヒーは100円でしたが、今では130円や140円でないと買えません。同じ缶コーヒーなのに、必要なお金が増えている──これはつまり「お金の価値が下がった」ということ。だから、結果として貯金だけでは目減りしてしまうのです。



どんどん物価が上がっているので、同じものを買って生活しているのに家計が徐々に苦しくなってしまいます。
金の「価値保存」という性質:年収と住宅を金の重量で表すと・・・?
金の価値をもっともわかりやすく示す例が「兵士の年収」と「家の価格」です。
まず兵士の年収を見てみましょう。古代ローマの兵士は、1年働くとおよそ200〜300gの金に相当する給料を得ていました。衣食住をまかなうには十分な額だったそうです。
現代でも状況はほとんど変わりません。アメリカの兵士(下士官クラス)の年収はおよそ3万ドル。これを金価格1g=17,000円で換算すると約270gの金に相当します。
つまり、2000年を超えても「兵士の1年分の労働=数百gの金」という関係は変わっていないのです。
次に家の価格を見てみましょう。アメリカの住宅価格を金の重量で換算したデータでは、
- 1890–1933年:5.1〜9.5kg
- 1971–1981年:2.3〜15.8kg
- 2012–2019年:2.8〜5.0kg
つまり、100年の時を超えて「家一軒=およそ5kgの金」で建てられるという関係は大きく崩れていません。(参考:米国の住宅価格を金で換算した記事 How Much Gold Does It Take to Purchase a Home?(Elemental))
このように、兵士の年収=300g、家=5kgという基準がほとんど変わらないことこそ、金が世界共通の「価値保存の手段」と呼ばれる理由なのです。



金は「2000年前でも100年前でも、今でも同じ価値を保っている」資産です。だからこそ、純金積立で少しずつ金を持つことには、インフレや通貨安から資産を守る意味があるんですね。
金は最も安定した物質:腐らず錆びず価値を保つ
金が長い歴史の中で価値を保ち続けてきたのは、単なる偶然ではありません。それは金が 最も安定した物質 であり、さらに 産出量が限られている という二つの特性を兼ね備えているからです。
- 安定性:鉄は錆び、銅は緑青が出るが、酸やアルカリにもほとんど反応せず錆びない。数千年前の金製品が今もそのまま残っている。
- 希少性:地殻中に含まれる量はごくわずかで、新たに採掘できる量にも限りがある。
つまり、金は「安定性」と「希少性」という二つの条件を同時に満たす、極めて特別な物質なのです。



金は長い歴史の中で人々の資産を守る手段として選ばれてきたのです。
詳しい科学的な背景については、こちらの記事で解説しています。


ビットコインも金をモデルにした価値保存の仕組み(余談)
余談ですが、近年ますます注目されているビットコインも「金」に似た仕組みを持っています。
勝手に増やせない金は埋蔵量が限られていて、掘り出すのに多大な労力が必要です。ビットコインも発行上限(2100万BTC)がプログラムで決められており、誰も勝手に増やすことはできません。
金は物質として非常に安定しており、腐ったり錆びたりすることがありません。ビットコインはブロックチェーン技術によって守られ、改ざんには膨大な計算力が必要になるため、実質的に不可能です。
このように、金が「物質としての安定性」で価値を保つのに対し、ビットコインは「数学的・システム的な安定性」で価値を守っていると言えます。



ただし、数千年にわたる実績がある金に比べ、ビットコインはまだ歴史が浅く、安定性では金に一日の長があると思っています。
純金積立とは、初心者でも安心して始められるインフレ対策
ここまで「金を保有する意味」について説明してきましたが、実際に金を持つ方法としておすすめなのが純金積立です。なぜなら、毎月少額から自動的に積み立てるため、毎日の価格について深く考えることなく、初心者でも始めやすいからです。
現物の金貨やインゴットを一度に購入するのはまとまった資金が必要で、保管や盗難のリスクもつきまといます。その点、純金積立なら銀行口座からの引き落としでコツコツと買い続けられ、保管された金は必要に応じて現物を引き出すことも可能です。



純金積立は、「インフレ対策として金を持ちたいけれど、手間やリスクは避けたい」という人にとって最適な仕組みです。
純金積立による購入:ドルコスト平均法により値下がりリスクを低減
純金積立の最大の特徴は「毎月一定額を自動的に積み立てられる」ことです。たとえば月1万円を積立設定すると、金価格が高いときには少ししか買えず、金価格が安いときには多く買うことになります。この仕組みをドルコスト平均法と呼びます。
ドルコスト平均法を使うと、毎回の購入単価が平均化されるため、相場が一時的に下がったとしても購入コストが平準化され、リスクを抑えられるのがメリットです。
毎月1万円積立する場合
- 金価格が1g=10,000円のとき → 1g購入
- 金価格が1g=5,000円のとき → 2g購入
- 金価格が1g=20,000円のとき → 0.5g購入
このように、自動的に「高いときに少なく、安いときに多く」購入することになるため、長期的に見ると平均購入単価が下がりやすくなります。



私自身、6~7年前に純金積立を知人へ紹介した勧めたことがあります。その方はその時に純金積立を始めたらしく、先日「倍以上になってる~」と喜んでいました。
もちろん、ドルコスト平均法は「必ず得をする」仕組みではありません。金価格がずっと右肩上がりの場合は、一括購入した方が有利になることもあります。しかし、将来の価格が読めない金投資においては、リスクを分散する合理的な方法として広く利用されています。
保管方法を知ろう:「特定保管」と「消費寄託」
特定保管(混合・混蔵寄託)とは?
特定保管は、金融機関や業者の財産とお客様の資産をきちんと分けて管理する方法です。たとえば純金積立の場合、業者が保有する金と利用者が積み立てた金を明確に区別して保管します。
消費寄託とは?
一方、消費寄託は「お客様が預けた金の所有権を業者が引き取り、同じ量の金を受け取る権利だけを持つ」という仕組みです。



どちらの方法でも引き出せば現物の地金を手にすることができるというところでは同じです。
純金積立どっちがおすすめ?:最安の手数料は楽天証券
純金積立を選ぶときに意外と大きな差になるのが手数料と地金引き出し手数料です。毎月の積立額が同じでも、長期間続けると数万円以上の差になることもあります。
下の表が純金積立のサービスがある金融機関の手数料などサービス料をまとめたものです。保管料と年会費は条件はあるもののほぼ無料が一般的なようです。
手数料、地金引出しの部分で差があるので確認しましょう。(※筆者調べですので詳細な条件などは各社HPを確認お願いします)
| 口座 | 手数料 月¥10,000積立 | 保管方法 | 保管料 | 年会費 | 地金引出し 100g |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 1.15%* | 消費寄託 | ¥0 | ¥0 | ¥5,500 |
| SBI証券 | 1.65% | 特定保管 | ¥0 | ¥0 | 都度(1kg毎) |
| 田中貴金属 | 2.50% | 特定保管 | ¥0 | ¥0 | ¥18,700*** |
| 三菱マテリアル | 2.60% | 消費寄託** | ¥0 | ¥0 | ¥10,450 |
** 特定保管(混蔵寄託)も選択できるが保管料が有料
***2025年12月16日より



楽天証券で楽天カード決済での純金積立をすると最も手数料が安くなるようです。地金の引出しも手数料が安いので手数料重視であれば楽天証券が最有力です。
ただし、投資はご自身の判断で行なってください。
純金積立Q&A:NISAを利用したい場合を解説
- NISAで純金積立はできますか?
-
残念ながら、NISAで直接「純金積立」を行うことはできません。NISAは株式や投資信託などの金融商品を非課税で運用できる制度だからです。ただし、証券口座を通じて 「金ETF」 を購入することは可能です。つまり、NISAで持てるのは「金融商品としての金」であり、純金そのものを積み立てる仕組みではありません。金ETFについてはこちらをご覧ください。
SIFT-LAB
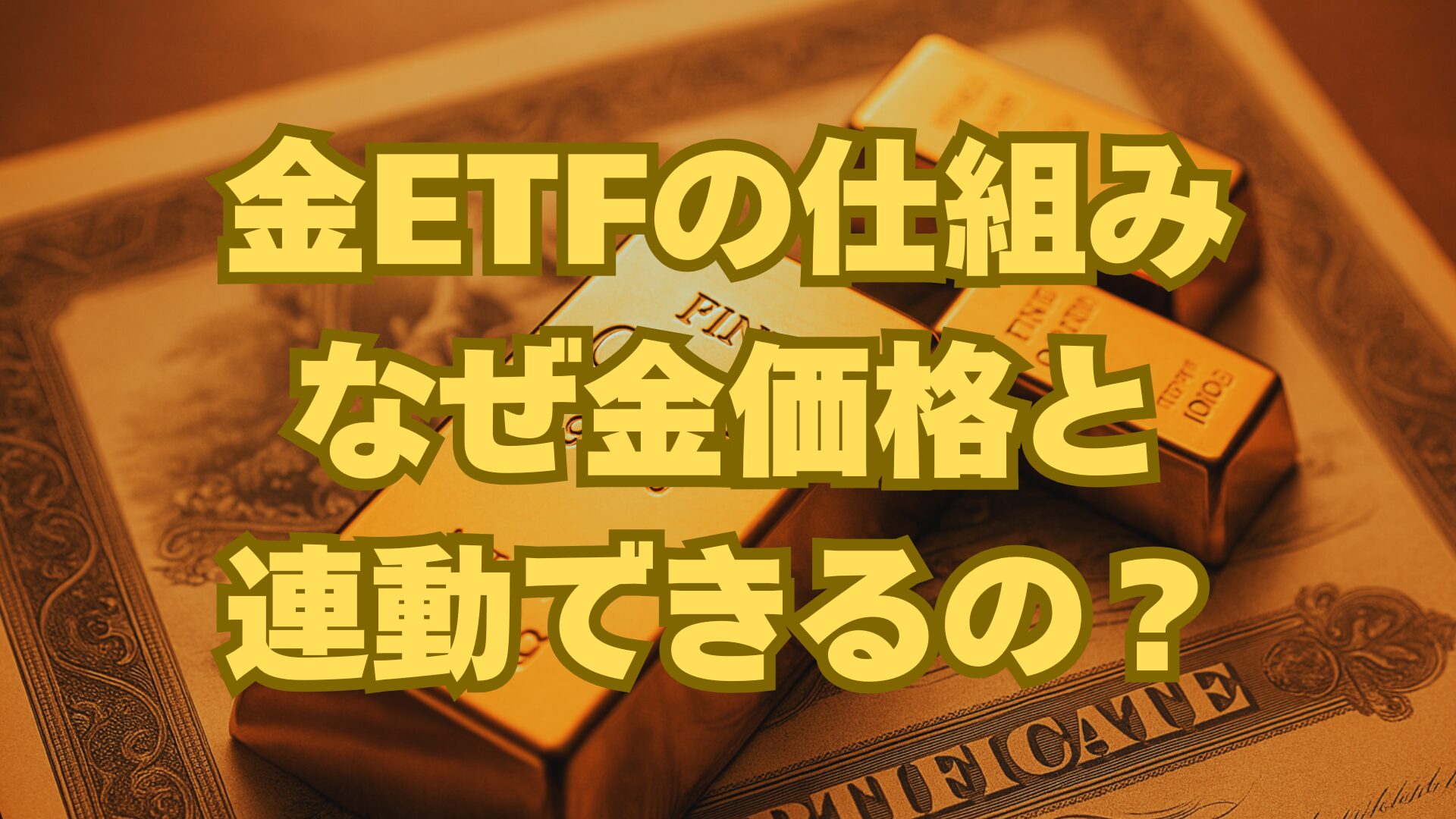 金ETFの仕組みとは?価格が連動する理由をやさしく 金ETFはどうして金の価格と連動するの?運用会社や信託銀行、指定参加者など4者の関係性から、金ETFの仕組みとその魅力をわかりやすく解説します。
金ETFの仕組みとは?価格が連動する理由をやさしく 金ETFはどうして金の価格と連動するの?運用会社や信託銀行、指定参加者など4者の関係性から、金ETFの仕組みとその魅力をわかりやすく解説します。 - 金ETFと純金積立の違いは何ですか?
-
金ETFは金価格に連動する金融商品です。株式と同じように市場で売買でき、手数料が低いというメリットがあります。ただし、金ETFはあくまで金融商品なので、現物の金を引き出すことはできません。一方、純金積立は積み立てた金をインゴットや金貨として引き出せるのが最大の特徴です。「実際に本物の金を資産として持ちたい人」には純金積立の方が適しています。
SIFT-LAB
 純金積立 vs 金ETF|始めるならどっちが得?税金・違い・メリットを徹底比較 金投資を始めたいけど、純金積立と金ETFのどっちがいい?現物保管・NISA対応・税制(課税方式)の違いを表でわかりやすく比較します。
純金積立 vs 金ETF|始めるならどっちが得?税金・違い・メリットを徹底比較 金投資を始めたいけど、純金積立と金ETFのどっちがいい?現物保管・NISA対応・税制(課税方式)の違いを表でわかりやすく比較します。 - 現物(金貨やインゴット)保管と純金積立の違いは?
-
現物(金貨やインゴット)を直接購入する場合は、手元に実物を置ける安心感があります。しかし、その分「まとまった資金が必要」「盗難や保管のリスクがある」というデメリットもあります。純金積立は、数千円からコツコツ積み立てられ、自動的にドルコスト平均法が働くのが強みです。必要に応じて現物を引き出すこともできるため、現物と積立の“いいとこ取り”ができる仕組みと言えます。
まとめ:純金積立はコツコツ派に最適な資産形成法
純金積立は、少額から始められ、値動きを気にせずに続けられる投資方法です。ドルコスト平均法により購入単価が平均化されるため、相場が下がったときでも安心して積み立てられるのが大きなメリットです。
また、楽天証券やSBI証券、田中貴金属など、サービスごとに手数料や保管方法、地金の引き出し条件に違いがあります。
- 手数料の安さを重視するなら楽天証券
- 安心感のある特定保管を選びたいならSBI証券や田中貴金属
といった形で、自分の目的に合わせて選ぶとよいでしょう。
純金積立は「今すぐ大きなリターンを狙う投資」ではありません。しかし、インフレや円安といった将来のリスクに備えるための着実な資産形成の手段として、長期的に力を発揮します。



積立は放っておいても自然と続けられるという特徴もありますので、長期的なインフレから資産を守るために、ご検討されてはいかがでしょうか。将来気がついた時に増えてる!ということになるかもしれません。
ここまで読んでいただきありがとうございました。ご質問などある場合は問い合わせフォームよりお願いします。
【免責事項】
本記事は特定の金融商品・投資手法の勧誘や推奨を目的としたものではなく、情報提供を目的としています。投資には価格変動リスクが伴い、元本割れの可能性があります。ご自身の判断と責任のもと、慎重にご検討ください。
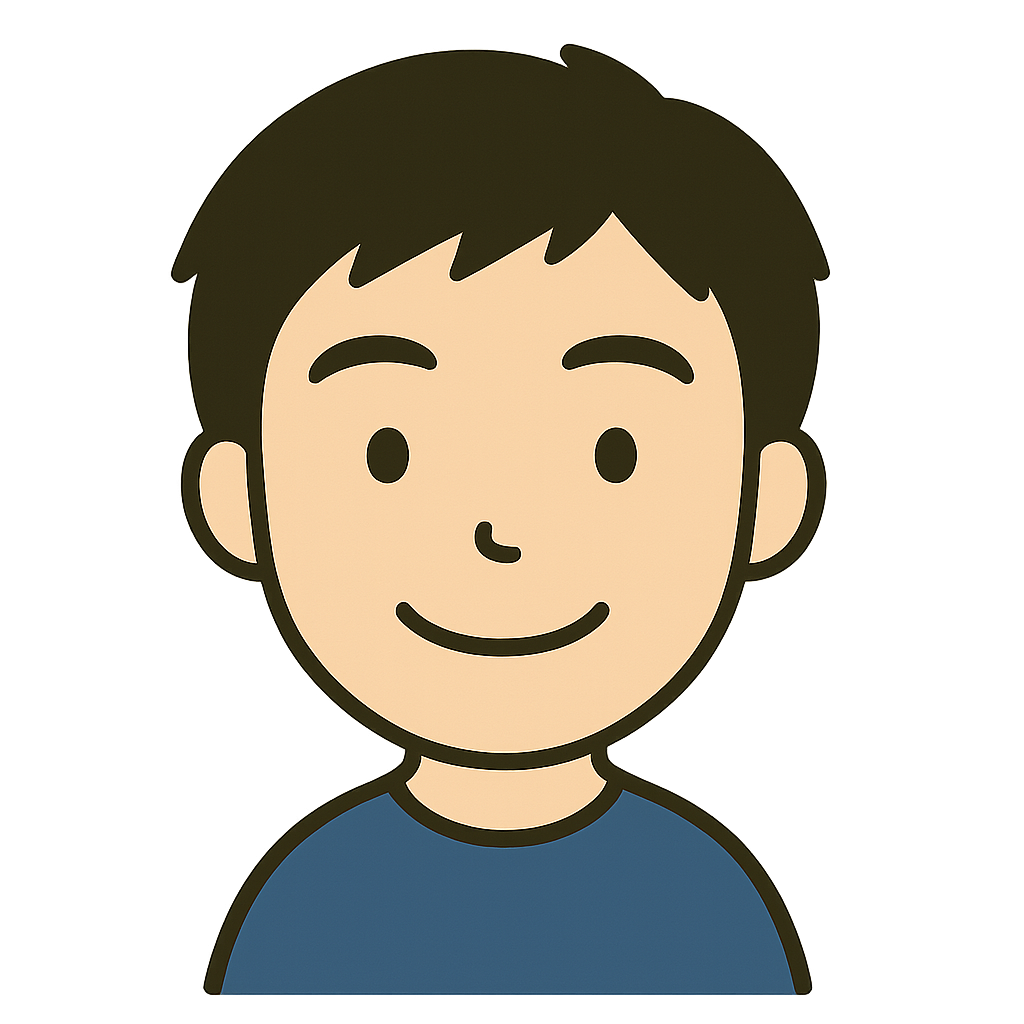
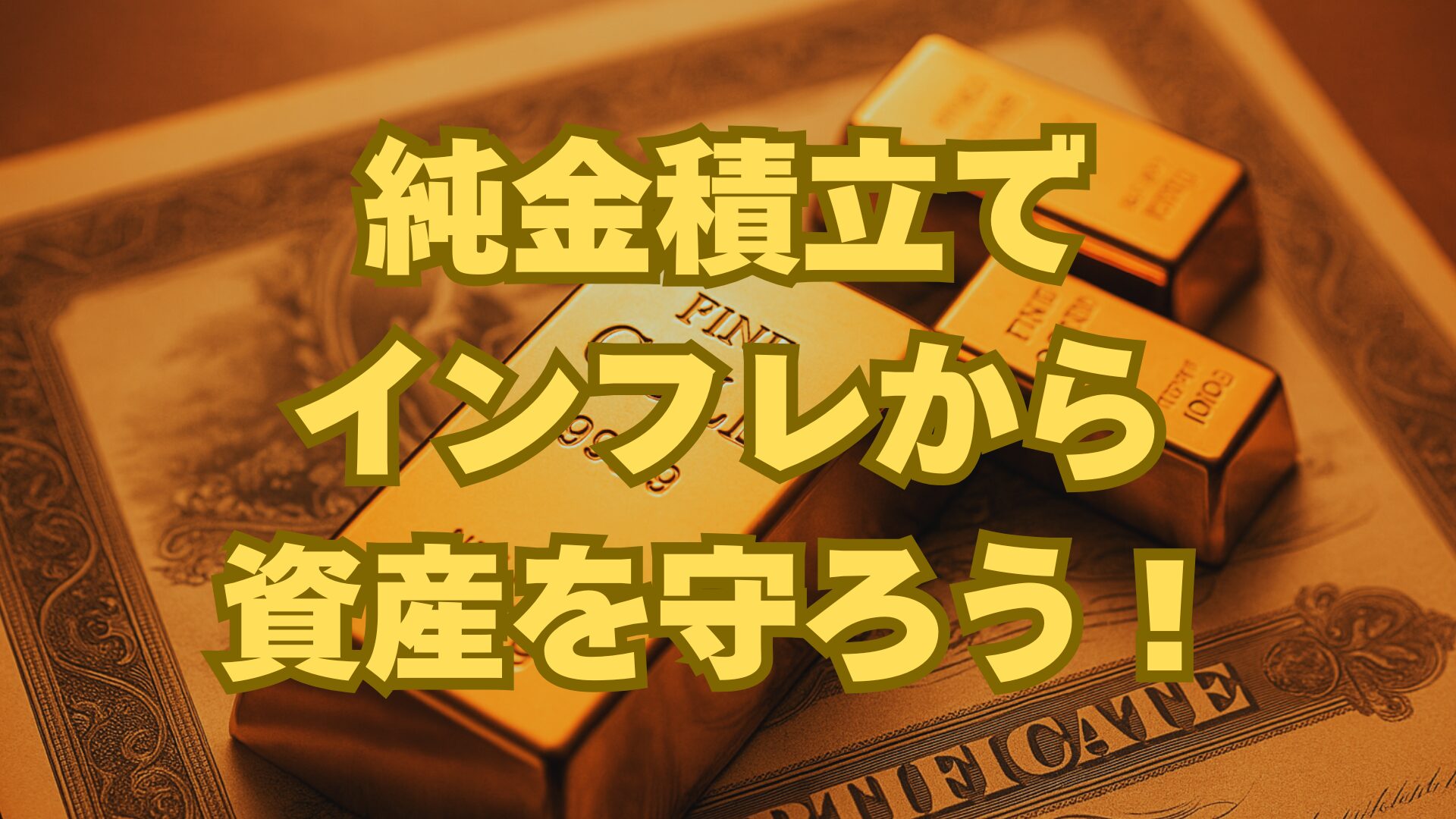
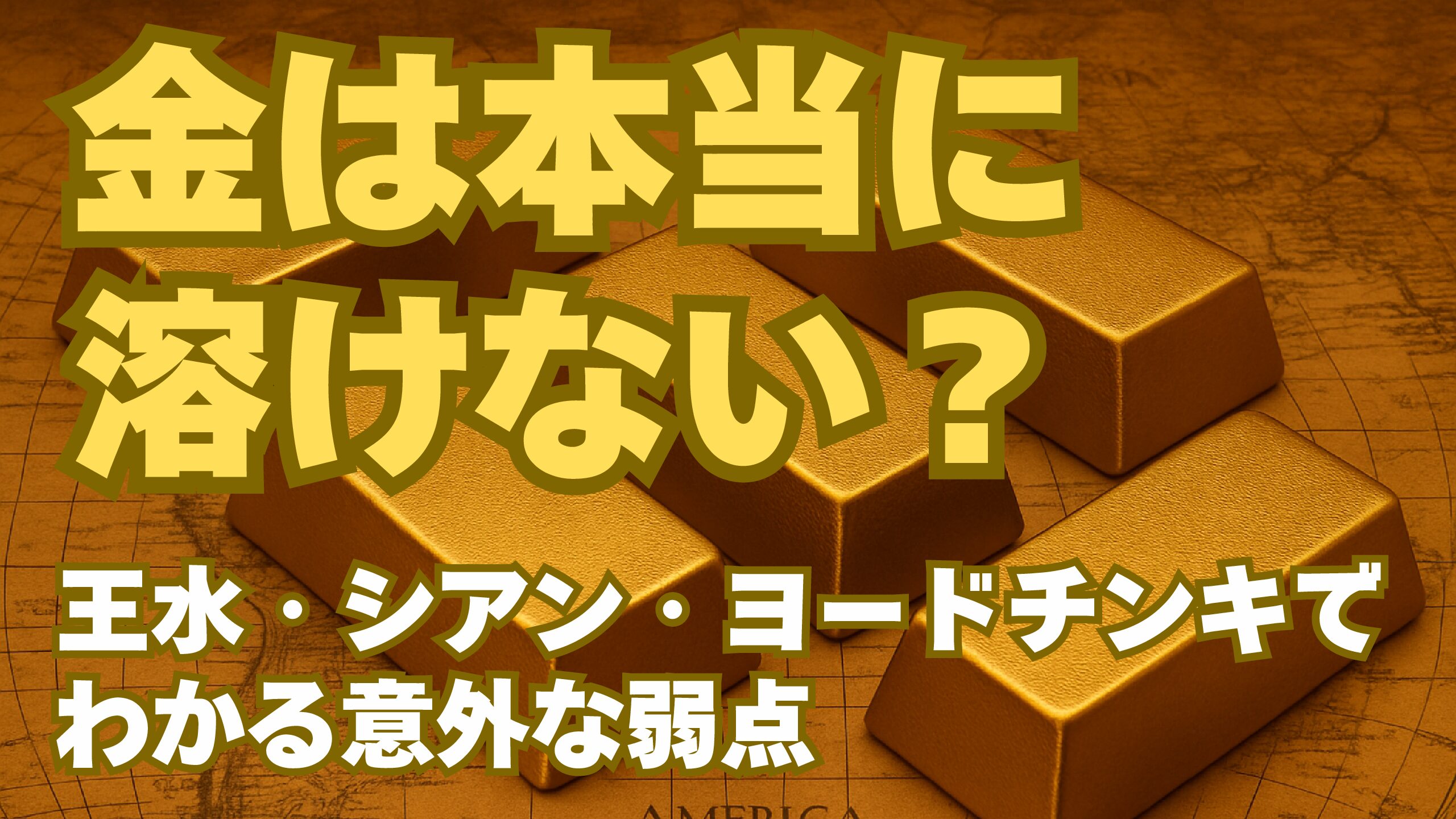

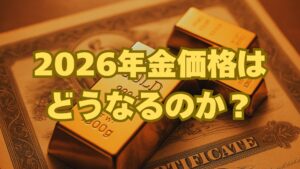
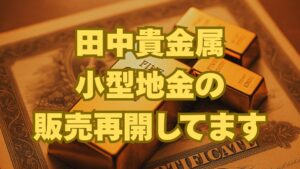
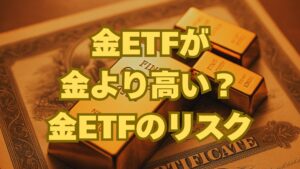


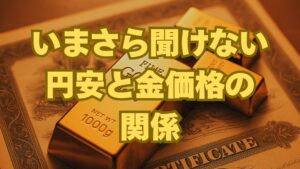
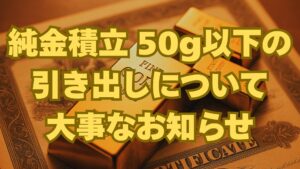
コメント