「金を作りたい」。 この欲望こそが、人類を“化学”、ひいては”科学”へと導きました。
現在、私たちが当たり前のように使っている「化学(chemistry)」という言葉は、 もともと「錬金術(alchemy)」を語源としています。 そしてその錬金術は、まさに“金”を生み出す夢から始まったものでした。
この記事では、「金を作る」という人類の幻想が、 いかにして現代の科学へとつながっていったのかを追いかけます。
錬金術とは?──金に憑かれた人類の夢
古代の人々にとって、金は単なる「金属」ではありませんでした。腐食せず、いつまでも輝きを保ち、他のどの金属とも異なるその特性により、金は「神の金属」や「永遠の象徴」として崇められました。その物理的な安定性と美しさから、金は“完成された金属”として他とは一線を画していました。
こうした金への執着は、「他の金属から金を作り出す」術、すなわち錬金術を生み出します。
西洋では、ギリシャの四元素説(火・水・土・空気)を基に、 鉛などの“未熟な金属”を“完全な金属=金”へと変化させる試みが始まりました。 これが哲学・宗教・自然観が混じり合った「alchemy(アルケミー)」の始まりです。
一方、東洋(中国)では「不老不死の霊薬(丹)」を目指す錬丹術が発展しました。 こちらもまた金・水銀・鉛などを用いて、人間の寿命や肉体までも変えようとしたものです。
つまり、金を作るという夢は、単なる物質変化の探求ではなく、 世界の真理や永遠性を追い求める哲学的・宗教的探究でもあったのです。
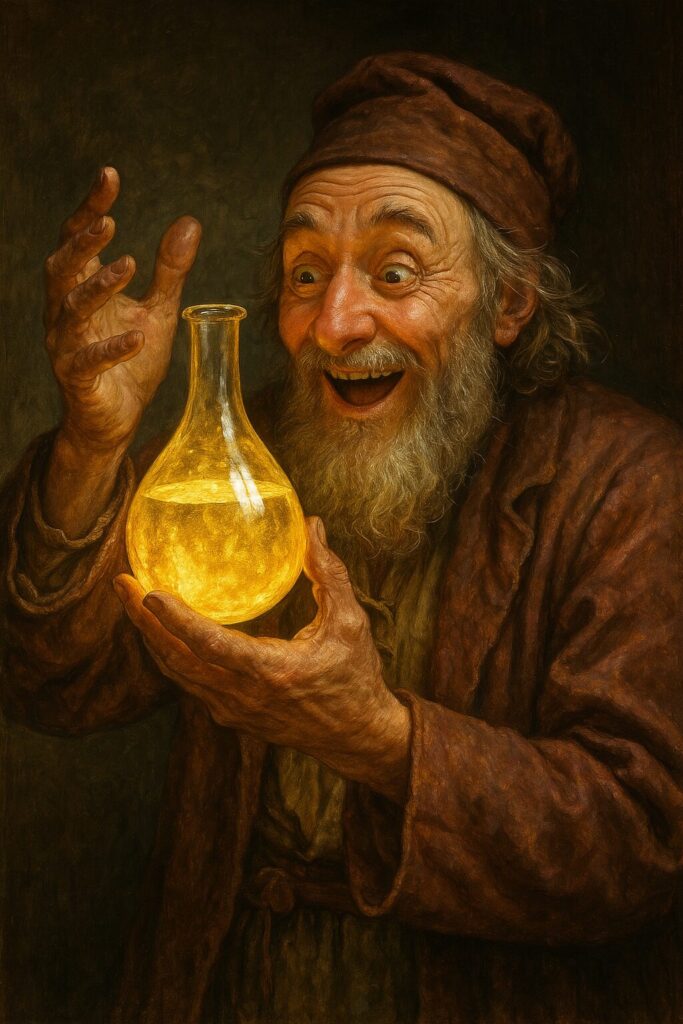
錬金術から生まれた「実験という考え方」
錬金術師たちは、実際にさまざまな物質を混ぜ、熱し、冷やし、結晶化させることで、 金に似た物質や奇妙な反応を得ようとしていました。
この過程で、今日の化学実験にも通じる技術が次々と生まれました:
- フラスコ、蒸留器、坩堝などの実験器具
- 加熱・蒸留・沈殿といった基本操作
- 酸・アルカリなど物質の性質に関する観察
現代の私たちから見れば「迷信」にも見えるこれらの実験の積み重ねが、 やがて再現性と定量性を重視する「化学」への第一歩となっていきます。
あの有名な科学者も錬金術師だった?
意外なことに、近代科学の基礎を築いた多くの偉人たちも、錬金術に強い関心を抱いていました。
アイザック・ニュートン
万有引力や微積分で知られるニュートンは、生涯にわたって錬金術の研究を続けていました。 残された手稿の約100万語以上が、錬金術に関するものだったとされています。
ロバート・ボイル
「近代化学の父」と呼ばれるボイルもまた、 錬金術師の実験技術や思索から多大な影響を受けています。
彼らにとって錬金術は、金を生み出す術であると同時に、 「物質の本質」を探るための哲学的手段でもあったのです。
錬金術は失敗だったのか?
錬金術師たちは、結局“金”を作ることには失敗しました。 けれどもその過程で、
- 「観察によって自然を理解する」
- 「再現性ある方法で物質を操作する」
- 「仮説と検証を通して世界を知る」
といった科学の基本姿勢を育んだのです。
その意味で、錬金術は失敗ではなく、科学の母だったと言えるでしょう。
おわりに:金から始まった科学の物語
「金を作りたい」という幻想を追い求める中で、真鍮などの新物質を作り出していきます。そして、新しい材料を作ることができるという技術とその学問に変化しました。
化学は、まさにこの人間の欲望と知性が交わるところで生まれた学問です。
次回の記事では、錬金術師としてのニュートンの姿にさらに踏み込み、 彼がどのように“金”に取り憑かれたのか、そしてそこから得たものは何だったのかを探っていきます。
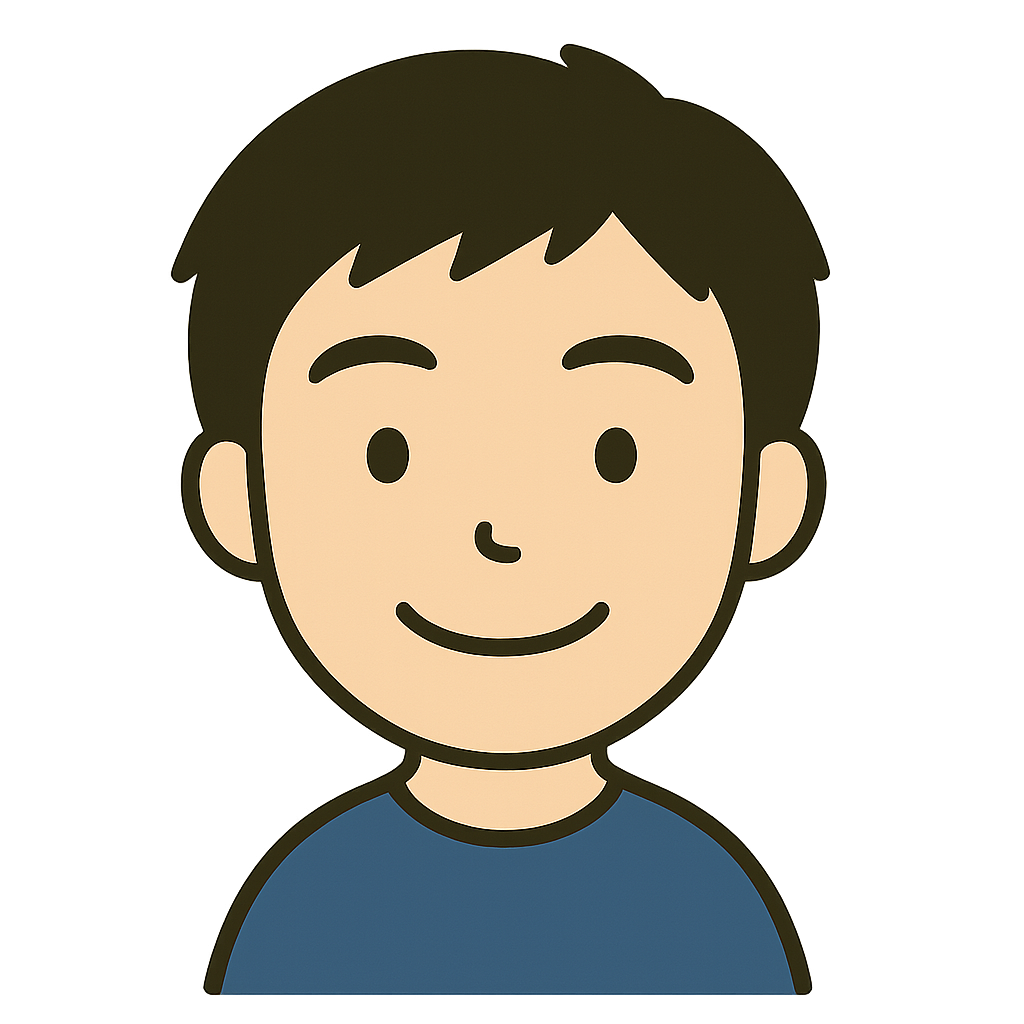
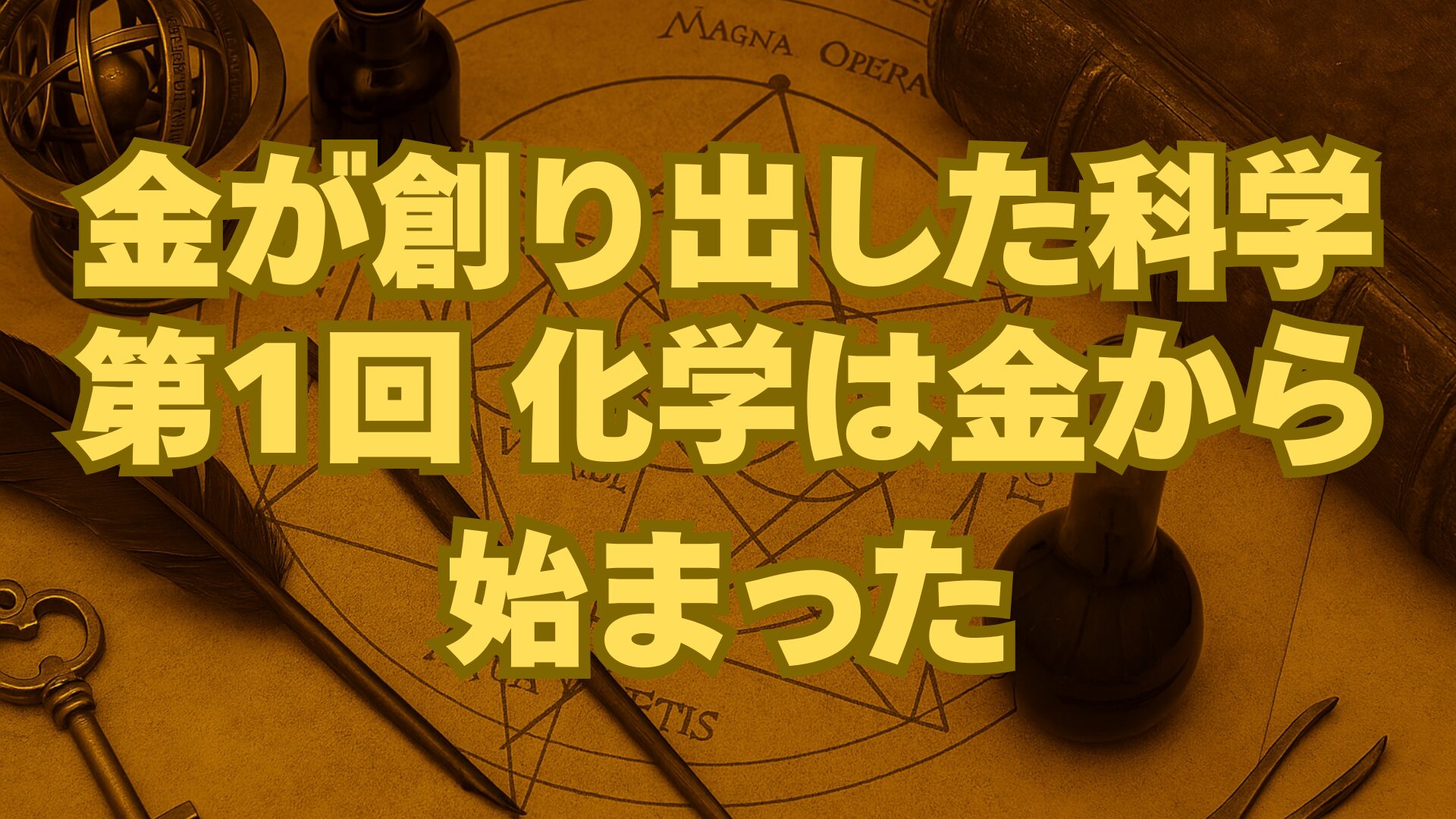
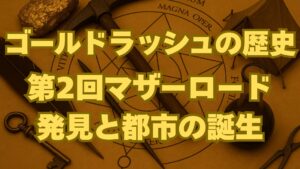
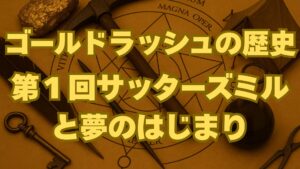
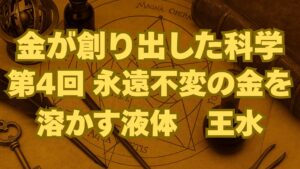
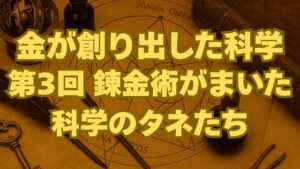
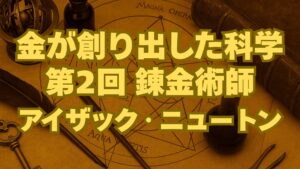
コメント