材料技術で読み解くゴールドの科学的価値

ゴルド博士、金ってどうしてあんなにピカピカしたまま錆びないの?他の金属はすぐ変色しちゃうのに、不思議だよね。

いいところに気づいたね。そこが金の、ほかの金属にはない特徴の一つなんだよ。今日はその秘密を、科学的な観点からじっくり見ていこうじゃないか。
はじめに|なぜ金だけは変わらず輝いていられるのか?
古代の遺跡から見つかる金の飾りが放つ輝きは、当時の人が見ていた輝きと大きく変わりません。こちらは世界最古の金装飾が発掘されたヴァルナ・ネクロポリスという遺跡です。紀元前4600-4200年ごろの埋葬地から発掘されたものですが、写真を見てもわかるように金装飾だけが異様に輝いています。

本記事では、金が錆びない理由を、科学の視点からわかりやすく解説します。
また、基本的に金は錆びることはありませんが、金を溶かすことも可能です。条件次第では金を腐食させることも起こり得ます。それについては別記事で解説しています。
金はなぜ錆びない?|その特徴とは
「錆びる」とはなにか
私たちが普段「金属が錆びる」と言うとき、それは空気中の酸素や水と反応して酸化されてしまう現象を言います。鉄が赤く錆びるのがそれですね。
でも金は、そうした酸素や水とほとんど反応しません。それだけではなく、ちょっとやそっとの酸でもびくともしません。他の金属は、酸素とくっついて化合物(サビ)になろうとしますが、金はそういう反応をほとんど起こさないのです。
そのため、地球上のほとんどの場所で、金はそのままの姿で安定しているのです。
一般的な金属(鉄・銀)と比べて何が違うのか
鉄は赤く錆びます。そして銀も黒く錆びてしまいます。これらは金属が酸素などと結びつき、単体ではなくなっていることを示しています。銀は空気中にあるわずかな硫黄と結びつくことで単体ではなくなります。※化学式が嫌いな方は下記は流してください。
鉄の酸化:4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 銀の硫化:2Ag + H2S → Ag2S + H2 ※りゅうか、と読みます。銀は硫黄化合物と反応すると黒くなり、その輝きを失います。こうしてみると、金はわずかな量の物質とも反応せずに、輝き続けていることになります。
金が錆びにくい理由
錆びない金はイオン化傾向で最強だった
通常、金属が「錆びる」とは、空気中の水分に溶け込んだ酸素と反応し、イオン化してしまうことを意味します。
たとえば鉄の場合、表面に付着した水分に含まれた酸素によって鉄イオン(Fe²⁺)になり、その後さらに酸化されて赤茶色の「錆(酸化鉄)」になります。
この錆は水に少し溶ける性質があるため、表面がはがれ、新しい鉄がむき出しになってしまいます。
そのため、錆はどんどん進行してしまうのです。
一方、金はまったく別格です。
空気中の水分にどんな物質が溶け込んでいても、金は反応しません。
金から電子を奪えるような物質は、大気中には存在しないからです。
たとえ濡れても、酸素にさらされても、少し酸性の環境になっても金は「無敵」です。
このように、「水の中でのイオンになりやすさ(=電子を手放しやすさ)」をイオン化傾向といいます。金(Au)は、このイオン化傾向が全ての金属の中で最も小さいのです。
まとめ
本記事では金が錆びないのは、金が最もイオン化しにくいことが理由であることを示しました。それはイオン化傾向という指標で表され、金は全ての物質の中で最もイオン化傾向が小さいのです。次回はイオン化傾向が小さい理由を金の電子構造から紹介していきます。

なるほど、金が錆びないのは科学的にもちゃんと理由があったんだね!ただの偶然じゃないんだ。

その通りだよ。だからこそ金は、古代から現代に至るまで、時を超えて輝き続ける特別な存在なんだ。
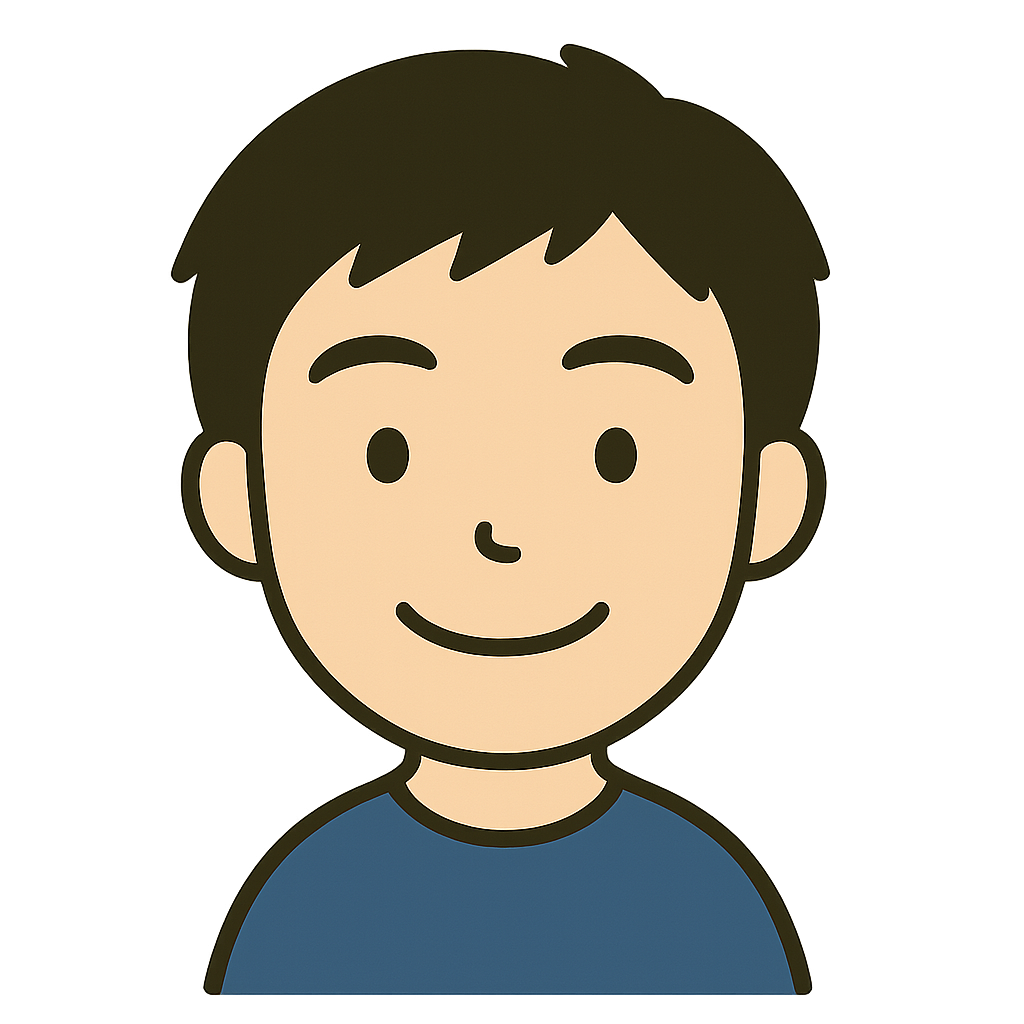


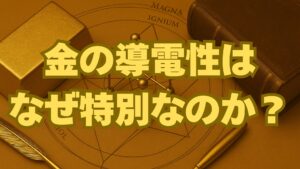
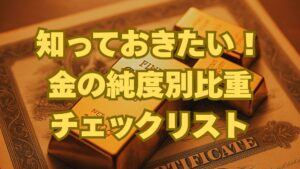
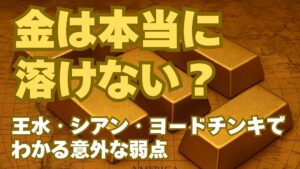
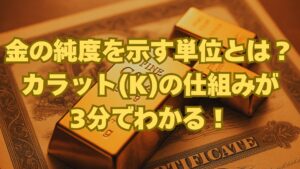


コメント