錬金術は「知のタネ」を無数に残しました。
科学は、それを並べ替え、選び取り、つなぎ合わせて、1つの構造にしました。
金を作ろうとした人類の試み――それが錬金術のはじまりでした。
けれどその過程で、金とはまったく別の価値が、静かに育ち始めていたのです。
バラバラな材料、成功とも失敗とも言えない実験、記録とも呼べない断片的な覚書。
そうした “未整理の知” が、後に科学という体系へと変わっていきました。
本稿では、錬金術が残した“科学のタネたち”という視点から振り返ってみます。

合金
錬金術師たちは、鉛や銅に鉱物や薬品を加え、加熱し、変化を観察しました。
その過程で、銅と亜鉛の合金である真鍮(しんちゅう)が、金に似た色を持つことが知られるようになりました。
真鍮や青銅は、それ以前から存在していた材料です。
しかし錬金術の中で、それらは「人工の金」に近い素材として扱われ、意図的に再現されるようになりました。
物質を理解し、「使いこなす」こと。
これが、材料科学への入り口だったのです。

実験方法
金を作る夢は、多くの実験を生みました。
蒸留、加熱、ろ過、沈殿、結晶化――。
今では当たり前の操作も、そのひとつひとつが、試行錯誤から始まったのです。
中東で生まれたアランビック蒸留器は、液体を精製する道具として発展し、
高純度アルコールや精油の分離に役立つようになりました。
器具と手法は、知識と切り離せません。
手を動かし、観察し、記録する。その繰り返しの中で、科学の作法が芽生えていきました。
言葉と分類
錬金術は、言葉にも痕跡を残しました。
たとえば、alcohol(アルコール)、elixir(エリクサー)、aqua regia(王水)――。
alcohol(アルコール):アラビア語の「al-kuhl(細かい粉末)」に由来し、蒸留によって得られる揮発性物質全般を指すようになりました。
elixir(エリクサー):アラビア語の「al-iksīr」が語源で、あらゆる病を治し、不老不死をもたらすとされた万能薬のことです。
aqua regia(王水):ラテン語で「王の水」という意味で、硝酸と塩酸の混合液。金を溶かすことができることから、貴金属の王にふさわしい液体とされました。
これらの言葉は錬金術の現場から生まれ、意味を持ち、やがて科学の言語へと吸収されていきました。どれも錬金術の現場から生まれ、意味を持ち、やがて科学の言語へと吸収されていきました。
また、物質を「火・水・風・土」に分ける四元素説も、今では間違った理論とされていますが、
「物を分けて理解しようとする態度」は、分類科学の出発点だったのです。
錬金術の価値
錬金術師たちは、目的(=金の生成)には失敗したかもしれません。
しかし、その過程で積み重ねられた知識、記録、試みは、のちの科学を支える土壌となりました。
散らばった知の断片は、科学という構造の中で再利用されたのです。
錬金術の本質は、「結果」ではなく「タネの蓄積」にありました。
科学はそのタネを、分類し、理論づけ、共有可能な知へと変えていきました。
そして私たちは、今も同じ営みを繰り返しています。
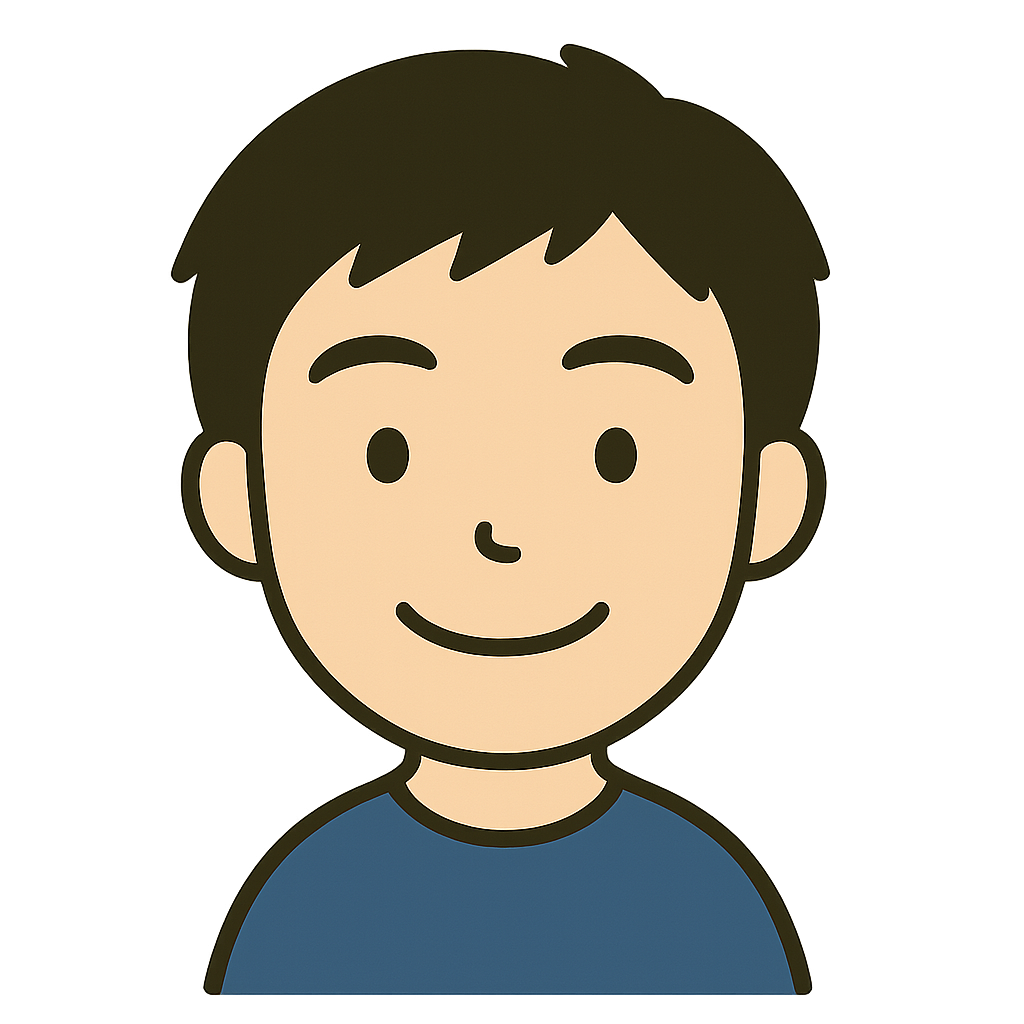
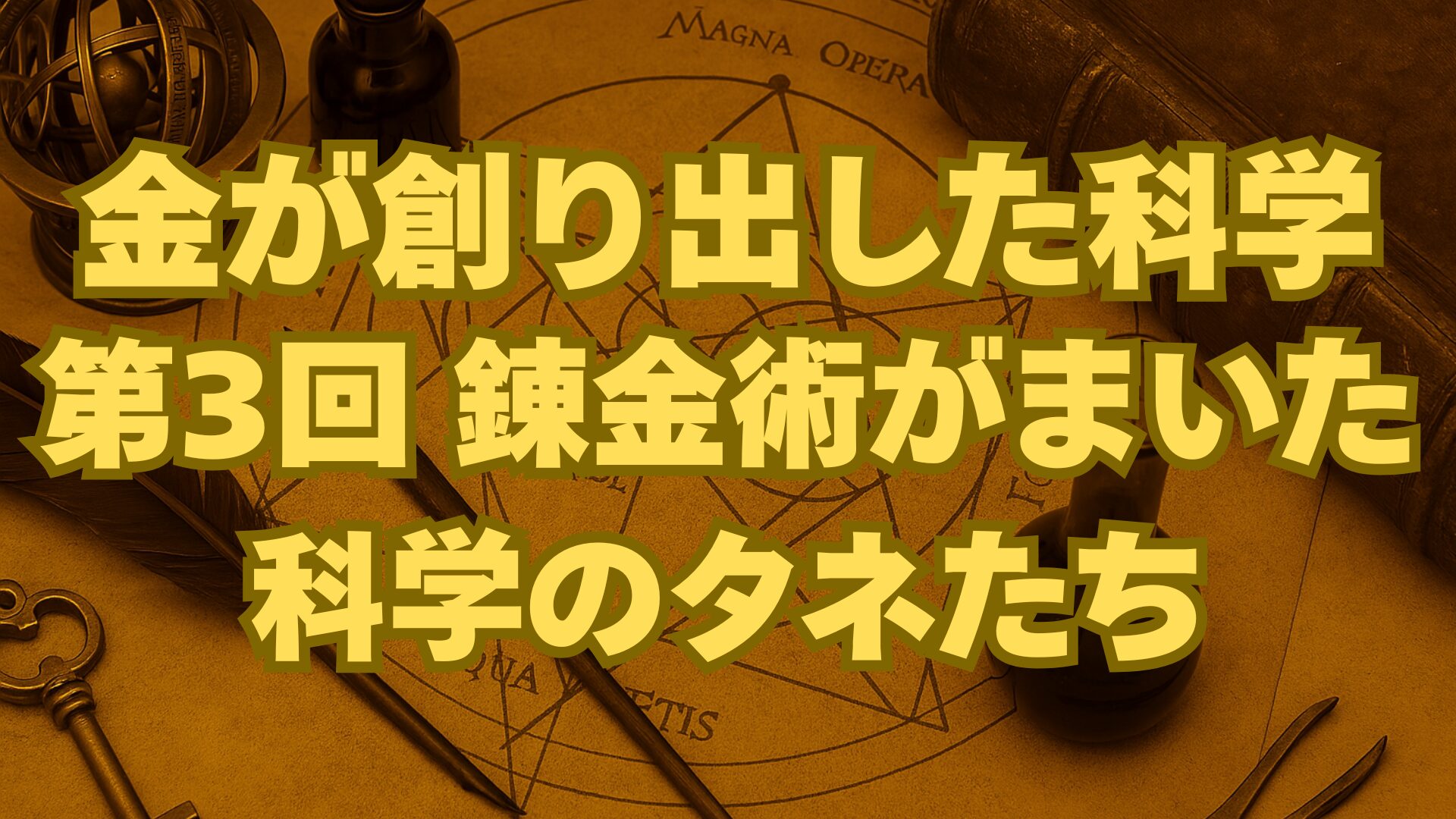
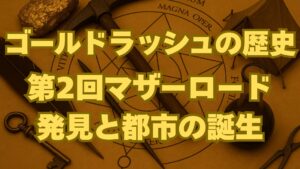
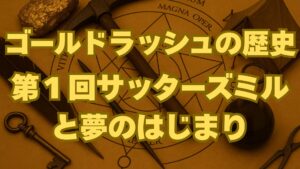
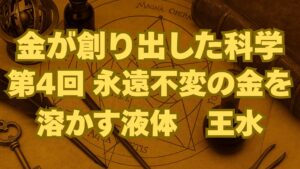
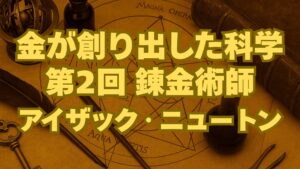
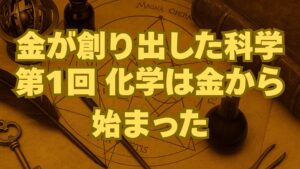
コメント