2025年10月27日、日本初のステーブルコイン「JPYC」が発行されました。最初に発行されたのは約1,500万円分。
たった2日で5000万円分以上のJPYCが発行されたようです。 このJPYCは現金(円)と日本国債を担保に発行されています。
ステーブルコインって何?って思う方もいるかと思います。今回はステーブルコインの仕組みを解説し、 金を担保にしたステーブルコインについて解説したいと思います!
 こうじ
こうじはじめにステーブルコインの仕組みについて誰にでもわかるように簡単に解説します!
ステーブルコインとは?
ステーブルコインは、いま使っている通貨(円・ドル)の価値に連動させて、ブロックチェーン上で安く・速く決済できるようにした新しいお金の形です。大事なポイントは決済の手数料が極めて安いというところです。
仕組み自体はビットコインなどの暗号通貨の技術(ブロックチェーン)を使います。暗号通貨というと価格の乱高下を気にしてしまいますが、価値が通貨と同じになるように、現金や国債などを裏付けとして発行する(=1コイン=1円や1ドルを保つ)点が特徴です。



つまり、価格は通貨と同じ、ということです!換金もすぐにできます!
暗号通貨の技術を使って、銀行を通さずにお金をやり取りができます。
「国が認めた支払い用ポイントのようなもの」です。
ステーブルコインのデメリット:円や国債を担保にする仕組みのリスクとは?
JPYCは、日本円や日本国債を担保にして発行されています。
10,000JPYCを発行するのに10,000円の国債もしくは10,000円の現金に相当するものが担保になっています。なので、逆にJPYCは円に換金もすぐにできます。これはステーブルコインの特徴の一つでもあります。一見すると、とても安定しているように見えますよね。
円は世界的にも信用の高い通貨ですし、日本国債は現状「安全資産」の部類です。



どれくらい安全なのでしょうか?
国債への信用がステーブルコインの土台
国債は、国の借金です。なので借金を返せるかどうかは国の信用そのものです。また、円を発行するときも国債を基にしています。つまり、円や国債を担保に発行するステーブルコインの価値を支えているのは、国の信用そのものなんです。
もし国の財政が悪化したり、金利が急上昇して国債価格が下がれば、その担保価値も揺らぎます。実際、アメリカや日本でも「国債の利回り上昇」「格下げ」といったニュースが増えてきました。これはつまり、「国債=絶対安全」という前提が崩れつつあるということです。
現在、日本ではJPYC、米国ではUSDT(テザー)やUSDCなど、いくつかのステーブルコイン銘柄が発行されています。これらの多くが「国債」や「現金」を担保にしており、国の信用を前提に価値を保っているのが共通点です。



国の信用でその安全性を保っているんですね。
通貨の信用は永遠ではない
通貨や国債の信用は国力に依存します。それは経済成長だったり、軍事力だったりします。経済成長が止まったり、財政状況が悪化すれば、どんな国でも「借りたお金を返す力」が落ちてしまいます。
つまり、円やドルを担保にしたステーブルコインは、「信用の上に成り立つ安定」にすぎません。これは裏を返せば、「国の財政への信用が揺らげば一緒に揺らぐ」ことを意味しています。
では、国家の信用に頼らず、より確かな“実物の信頼を基盤にした通貨は作れないのでしょうか。その答えのひとつが、「金(ゴールド)」を担保にしたステーブルコインです。
金を担保にしたステーブルコインとは?
ステーブルコインの基本は、「担保をもとに安定した価値を保つデジタル通貨」でした。では、その担保が“通貨”や“国債”ではなく、金(ゴールド)だったらどうなるでしょうか?
実はすでに、世界ではそのような試みが始まっています。代表的なものが、PAX Gold(PAXG) や Tether Gold(XAUT) と呼ばれる金担保型ステーブルコインです。
金の信頼 × ブロックチェーンの利便性
金を担保にしたステーブルコインの魅力は、時代の変化に左右されない金の「価値」とブロックチェーンの「使いやすさ・分割・送金の自由さ」を組み合わせている点で、新しい形のデジタルマネーです。
1トークンは実際の金と交換可能で、XAUTの場合、1トークン=スイスの金庫に保管されている現物の金1トロイオンスの所有権に対応しています。
つまり、
実物の金を、スマホで送れる時代になった。
金は通貨として使う場合、「分割するのが大変」「送るのも大変」「保管が大変」といった弱点を持っていました。金を担保とするステーブルコインはすべて克服する仕組みです。



最近、金現物の50g以下の引き出しが遅くなっているのも現物の金を分割するのが簡単ではないからでしょう!


金のトークン化で広がる新しい決済手段
この仕組みは「金のトークン化(tokenization)」と呼ばれます。ブロックチェーン上に「1トークン=金1g」といった対応関係を設定し、それを世界中で送金・保有・交換できるようにする技術です。数値上の問題となるため、1g =1トークンとした場合でも、0.01トークン(2025年11月現在で200円程度)を送金といったこともできるようになります。
これによって、これまで価値保存の象徴だった金が、流通できる資産へとアップデートできるようになります。



金の新しい使い道ですね!
金を担保にしたステーブルコインのメリットまとめ
ここまで見てきたように、金を担保にしたステーブルコインには次の3つのメリットがあります。
金という実物資産が裏付ける安心感
発行体や国の信用ではなく、金そのものが担保になっているため、有事にも強く、経済の変化に左右されにくい“実物ベースの安定性”を持ちます。
分割・送金・保管の課題を解決
ブロックチェーン上で分割した金を扱えるため、従来の「重い」「動かせない」「保管が面倒」といった金の弱点を解消します。
手数料が圧倒的に安く、決済が速い
ブロックチェーンを使うことで、銀行や仲介機関を介さずに国際送金でもほぼリアルタイムかつ低コストで送金・決済が可能になります。
金の信頼とブロックチェーンの利便性を組み合わせることで、「安定と使いやすさを両立した新しいお金」が生まれつつあります。



まだ発展途上ではありますが、今後の動きに注目したい分野です!
まとめ:金が再び「信頼の象徴」として動き出している
ステーブルコインは、デジタル時代の通貨とも言える新しい仕組みです。その中で、金を担保にしたステーブルコインは、「人が作った信用」と「自然が持つ信頼」を結びつける存在になりつつあります。
金のトークン化によって、これまで「動かない資産」だった金が、「デジタルで動く信頼の資産」へと変わり始めています。今後どこまで広がるかはまだ未知数ですが、この流れは、お金のあり方そのものを静かに変えていくかもしれません。



新しいものが好きなので早速入手してみたいと思います!
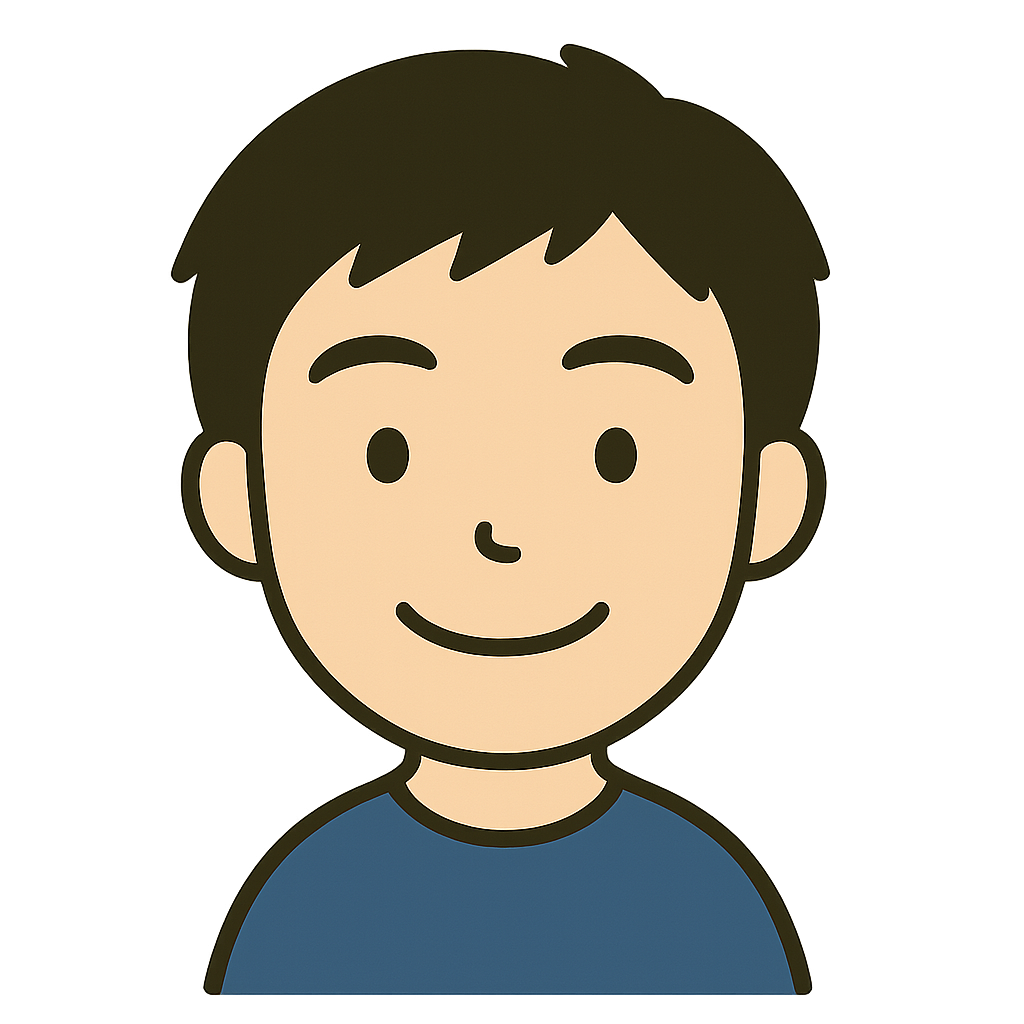


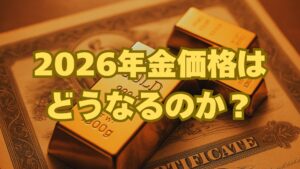
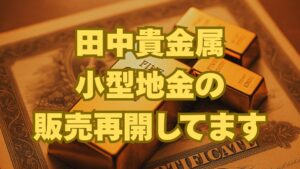
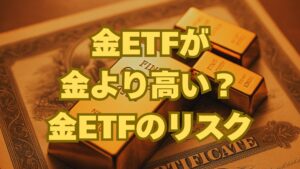

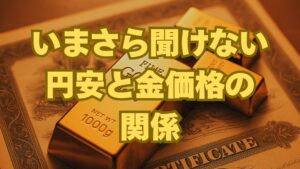
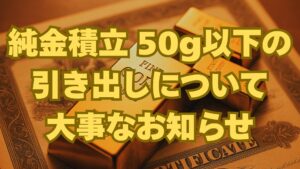
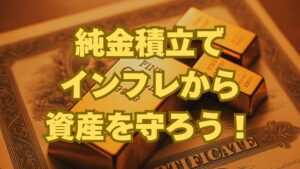
コメント