金(ゴールド)は、資産のどれくらいの割合で持つべきなのでしょうか?
2024年末から金価格はさらに上昇し、2025年に入っても高値を維持しています。これまで「資産の5〜10%を金に」というのが一般的な考え方でしたが、最近では「20%を金で持つべき」と発信する専門家もでてきており、保有比率をあげるという意見が増えています。
金は古くから「信頼の象徴」として人々に選ばれてきた資産です。一方で、現代の資産運用の主役といえば、やはり株式。金と株式――この2つの資産はどちらも「価値を持つもの」ですが、その成り立ちと意味はまったく違います。
 こうじ
こうじこの記事では、高騰を続ける金(GOLD)と株式の「価値の本質的な違い」を、投資初心者にもわかりやすく解説します!
金と株の本質的な価値の違い
金と株――どちらも「資産」であり、「価値を持つもの」です。しかし、この2つはまったく異なる原理でその価値を維持しています。
金は、自然から作られる価値です。人間が何をしようと、金は錆びず、腐らず、ほとんど変化しません。つまり「存在するだけで価値を保つ」もの。その安定性は、元素としての構造(Au=金)に由来しており、人の経済活動に依存しません。変わるのは人間の認識だけです。
一方、株は人間がつくる価値です。企業の活動、技術、サービス、そしてそこに寄せられる期待――それらの積み重ねが株価として通貨を使い評価されます。
株は人が生み出した価値を表しており、金は自然が生み出した変わらない性質に人間が見出した価値を保つ。この違いは、金は人間が見出した価値。株は人間が生み出した価値。つまり、両者の違いは単なる投資対象の差というより、発生の由来そのものが異なるのです。



金は生物が生まれるよりも太古の昔から存在しています!
金─自然が生み出す価値
金は、1971年にアメリカが金本位制を終了して以降、通貨の裏付けとしての役割を失いました。それでも、金の価値は50年以上経った今も揺らいでいません。それどころか、現代では再び注目を集める存在になっています。
【コラム】金本位制とは
かつて通貨は、一定量の金と交換できるように設計されていました。これを金本位制と呼びます。通貨の価値は「金の保有量」で裏付けられていたのです。しかし、1971年にこの制度を放棄し、世界は債権を裏付けとした信用による通貨へと移行しました。これはニクソン・ショックと呼ばれています。



昔はドルと金を交換できたんですね。しかしドルがどんどん増えてしまうと引き出しが多くなってきて困ってしまったようです。
近年、世界各国の中央銀行が金の保有量を増やしています。特に新興国を中心に買い増しが続き、この動きが金価格の上昇を支える大きな要因になっています。その背景にあるのは、基軸通貨であるドルの信用低下です。
巨額の財政赤字、地政学的リスク、国際秩序の変化――これらが重なり、ドルを中心とした通貨体制への疑念が高まっています。さらに、戦争や貿易摩擦などの不安定要素がこの流れを加速させています。
ロシア・ウクライナ情勢、中東情勢、米中対立――不確実性が増すほど、金の需要は高まり、価格は上昇します。人々は再び、最終的な価値の拠り所として金を選び始めたのです。つまり、金は再び“通貨の裏付け”としての位置を取り戻しつつあります。



特にロシア・ウクライナ情勢で、ロシアのドル資産を凍結したことが多くの国に衝撃を与えた、と言われています。
デジタルマネーやステーブルコインなどの新しい仕組みが登場する一方で、その価値の根底には今も「金」という物理的な裏付けが意識されています。
金は自然から採れる価値としては何も変わっていません。変わるのは人間の方であり、私たちはその不変の存在に、改めて価値を見出しているのです。
株─人間が生み出す価値
株式は、人が行う経済活動の価値を表す仕組みです。企業は資本や労働力、技術を使って製品やサービスを生み出し、社会の中で新たな価値を創出します。その成果が利益として現れ、株主はその利益の一部を分配金(配当)として受け取る権利を持ちます。
つまり、株式とは「人間の活動がどれだけ価値を生み出したか」を市場を通じて可視化したものなのです。
株価は常に変動します。それは企業の業績だけでなく、将来への期待や不安、社会全体の動きが反映されるからです。中でも重要なのが、インフレ(物価上昇)の影響です。インフレが進むと、モノやサービスの価格が上がります。企業の売上も名目上は増えやすくなり、その結果として株価も上昇する傾向があります。
もちろん、コスト増や金利上昇などの悪影響もありますが、長期的には株式はインフレに強い資産とされています。それは、株が人間の活動や生産の拡大に根ざした資産だからです。
一方で、金はインフレや通貨不安のときに価値が上昇することが多いですが、それは金の本質的価値が上がるからではありません。通貨への信用が低下した結果として、相対的に金への信頼が高まるのです。
金は自然の中で変わらない存在であり、変わるのはいつも「人間の認識」のほうです。つまり、金も株も人間の心理の上に成り立っています。金は「不変である価値」を認識する心理に支えられ、株式は「人間が生み出した価値」そのものに支えられています。
両者は対立するものではなく、人間社会における「価値の2つの側面」を表しているのです。



金は自然から生まれる価値、株式は人の活動から生まれる価値なんですね。
なぜ金の保有比率は「5〜10%」とされてきたのか
「金は資産の5〜10%を持つとよい」とよく言われます。この数字には明確な根拠があります。
2012年にWGCという団体から「日本の投資家にとっての金の最適保有比率」というレポートが発表されました。こちらでは980年代から2011年までのデータを使って「金の最適な保有比率」を分析しています。このレポートの結論として 2.9〜9.4% の金を保有するのが最適とされています(参考:「日本の投資家にとっての金の最適保有比率」(WGC, 2012年))。
これはつまり、金を保有することでポートフォリオ全体のリスクが下がることを示しています。このようにして導かれた「5〜10%」という数値は、2011年までの株や債券などの金融資産が「安定した信用」を前提に成り立っていた時代の指針でした。当時は現在に比べれば、各国の中央銀行のバランスシートも健全で、通貨への信頼が揺らぐことはまだありませんでした。つまり、金が10%を超えるほど必要になる状況は“想定外”だったのです。
それが、20世紀末から2010年代初頭までの常識でした。しかし、2012年以降の世界は大きく変わりました。リーマンショック後の景気回復策として、各国が前例のない規模で国債を発行し、中央銀行がそれを買い支える構図が続いています。国の債務残高は拡大を続け、通貨の裏付けとなる「信用」が少しずつ薄れてきているのが現状です。
金は、こうした“信用の劣化”に対して敏感に反応します。通貨への信用が保たれていた時代には「守りの10%」で十分だったものが、通貨の信用そのものが揺らぎ始めている今では、より高い比率で保有すべき資産へと変わりつつあるのかもしれません。



2011年には東日本大震災、2013年アベノミクス、2020-2022年にはコロナウイルスのパンデミックと2011年以降に大きな事件がありました。
これからの金保有比率はどう変わるのか
2024年9月以降、金価格はドル建てで大きく上昇しました。背景にあるのは、通貨への信頼低下です。これまでの世界経済は、米ドルを基軸通貨とするシステムに支えられてきました。各国が米国債を保有し、ドルを準備通貨として利用することで、通貨の安定と国際取引の円滑さが保たれてきたのです。
しかし近年、その前提が少しずつ崩れ始めています。巨額の財政赤字を抱えるアメリカでは、国債発行が常態化し、ドルへの“信用”は揺らぎつつあります。
同時に、米国債を大量に保有してきた新興国がリスク分散のために金を積極的に買い増していることも注目すべき動きです。事実、2023年以降、各国中央銀行による金購入量は過去最高水準に達しました。この動きは単なる短期的な投機ではなく、「基軸通貨ドルへの依存を減らす」という構造的な変化の表れと考えられます。
このような中で、金の位置づけは従来の“安全資産”から“通貨の裏付け”へと変わりつつあります。つまり、「債券の代わりに金を持つ」という考え方が現実味を帯びてきたのです。
過去の研究では「リスクを抑えるには金5〜10%」が最適とされていましたが、通貨の裏付けが国債という「信用資産」である限り、その信用が揺らげば、金の相対的な価値はさらに高まります。
現代の投資環境では、金を10〜20%程度まで引き上げることが合理的という見方も出始めています。(レイ・ダリオ氏https://www.gfa.co.jp/crypto/news/btc-news/news-1301/)



世の中の構造が変わってきているのは確かなようです。ただ、投資はあくまでも自己責任であることを忘れずに!
価値の由来──通貨の内側と外側
金と株は、どちらも「価値を持つ資産」です。しかし、その価値の由来は本質的に異なります。
自然がつくる価値:金
金(GOLD)は、地球が生み出した価値のひとつです。人間の活動に依存せず、化学的にも極めて安定した物質として存在します。その価値は、国や制度、約束に裏打ちされたものではなく、自然の安定性そのものに根ざしています。
金は通貨で「評価される」ものではありません。むしろ、金という不変の基準を使って、通貨の価値を「表している」にすぎないのです。
1ドルが何グラムの金に相当するか──
それが歴史的に「価値の測る手段」としての役割を果たしてきました。



5kgの金があればいつの時代でも家を買える。300gの金が平均的な年収に相当するといった話を下記のリンクで紹介しています。興味があれば見てみてください!
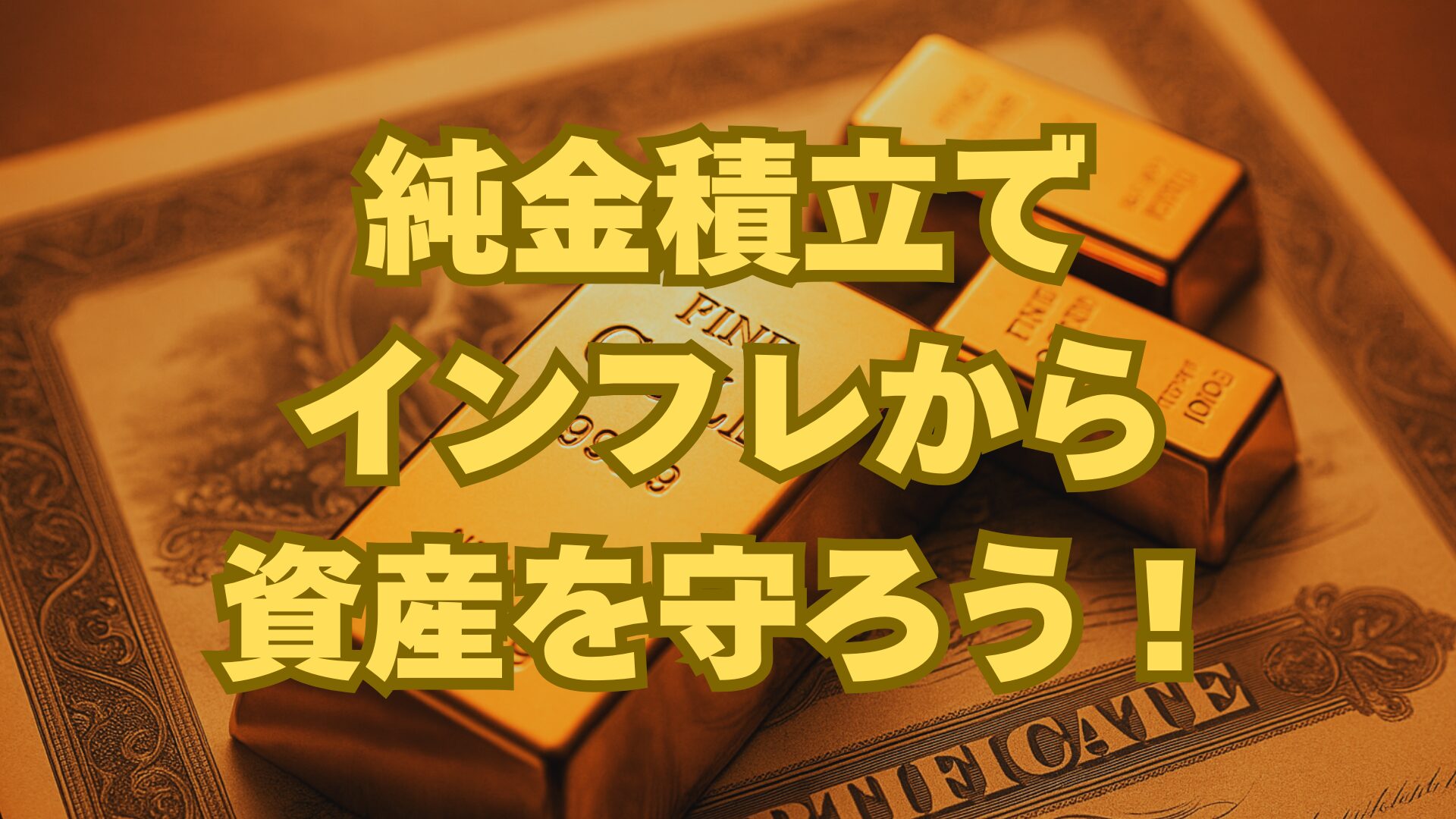
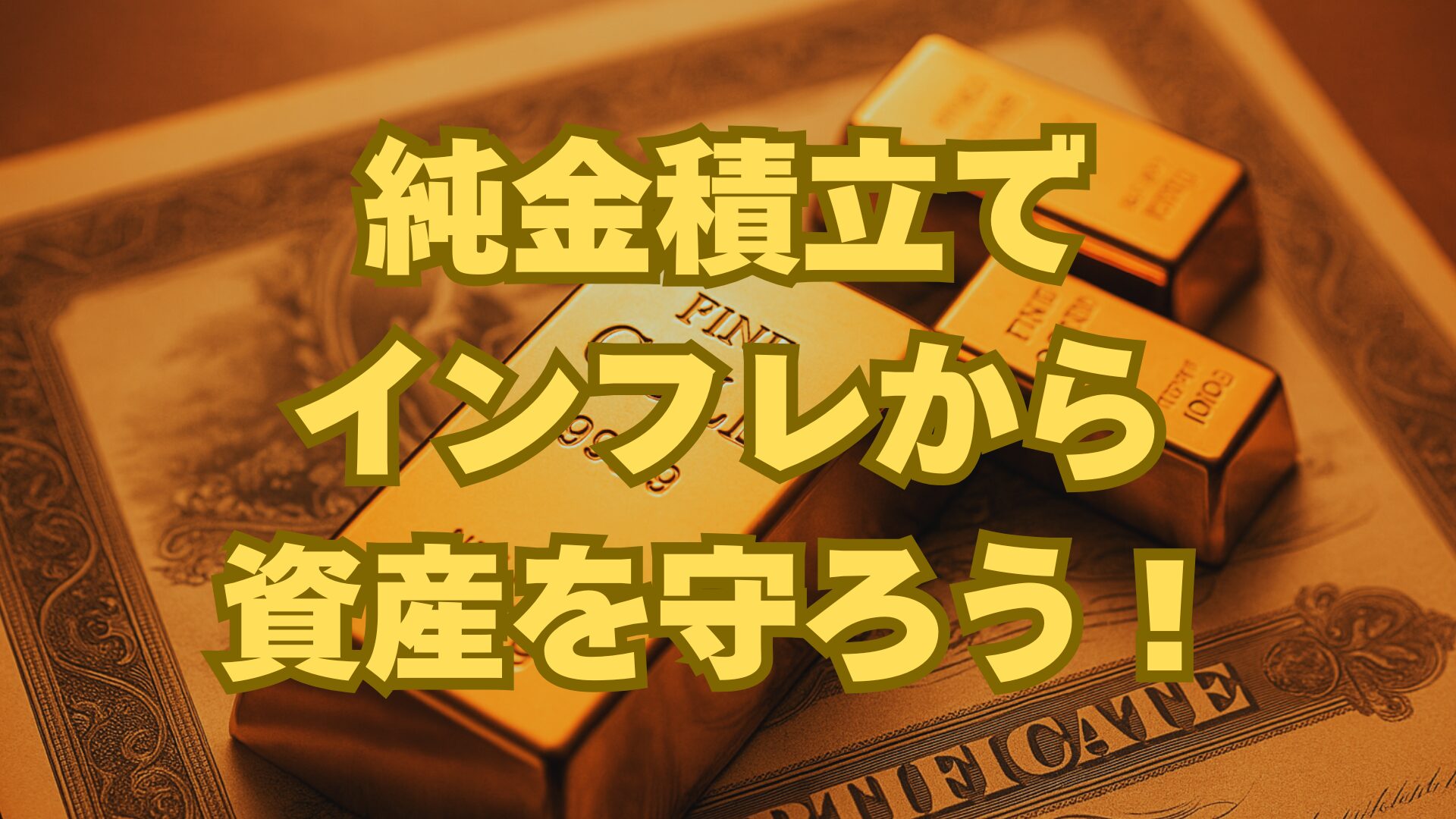
人がつくる価値:株
一方で、株式の価値は人間の活動から生まれます。
企業の成長、技術革新、社会の需要、そして投資家の期待。それらが積み重なって、株価という「数値の価値」が形成されます。しかし、その株価はすべて通貨という単位で評価されています。つまり、株の価値は通貨の価値を前提に成り立つものなのです。
通貨の信頼が揺らげば、たとえ企業が変わらず活動していても、その評価(株価)は不安定になります。株は人間の活動を映し出す鏡であり、通貨という“揺らぐ基準”の上に存在していると言えるでしょう。



株式の価値は人が生み出す価値の総体とも言えるのではないでしょうか!
通貨の外側にある基準
金は、人の活動がどれほど変化しても、その「物質としての価値」が揺らぐことはありません。それは通貨とは関係しないところで価値を持つ存在です。
一方、株や債券は通貨と密接に関係しており、その信用と共に上下する相対的な存在です。だからこそ、通貨の信頼が揺らぐ時代には、金という“通貨と関係のない基準”を一定量持つことが、資産を安定させる鍵になるのです。
これからの資産設計に向けて「価値を生み出す資産」と「価値を表す資産」。この2つのバランスをどう取るかが、これからの資産設計の重要なテーマになるでしょう。
金は、経済を成長させるわけでも、利益を生むわけでもありません。しかし、通貨の価値が変動しても変わらない“絶対的な基準となっています。それこそが、現代の不確実な経済環境において、金が再び注目されている理由なのではないでしょうか。



ここまで読み進めていただきありがとうございました!
今回は金と株式の価値の由来について考えてみました!
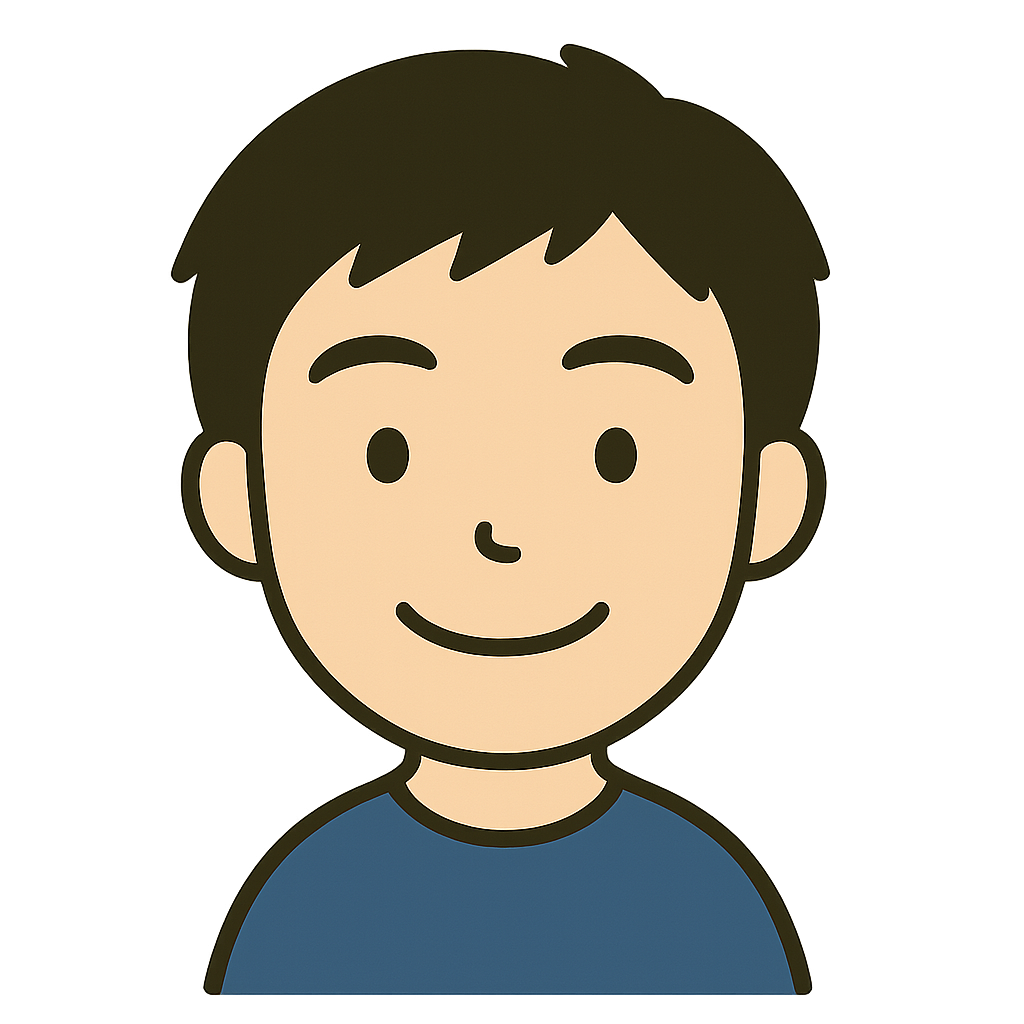
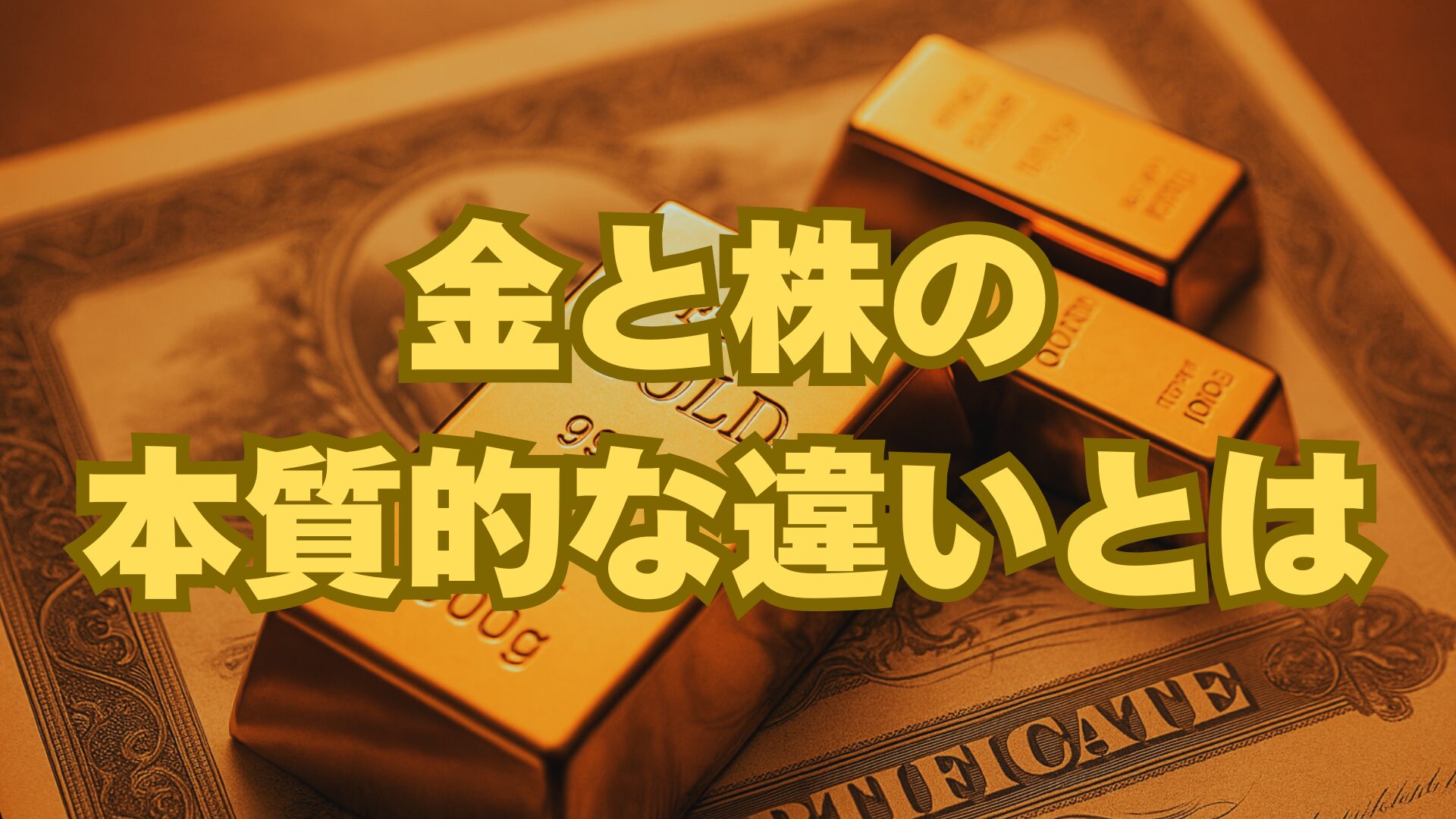

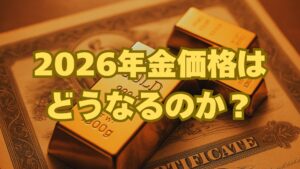
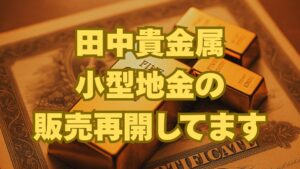
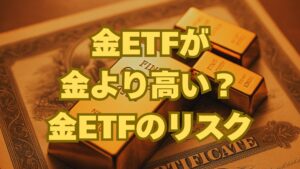

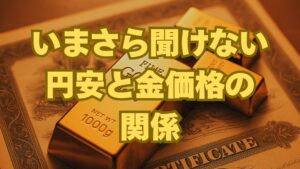
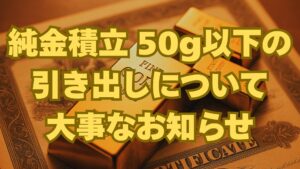
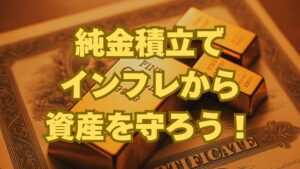
コメント